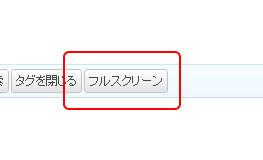翻訳本の楽しみは原著に劣ると、かたく信じていた時期がありました。
たとえば、書き出しの名文として名高い『雪国』の
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」
は、
「The train came out of the long tunnel into the snow country.」
になるそうで。
原文では汽車のことなど一言も言っていないうえ、悲しいことに国境がまるっと忘れられている。
確かに明快で意味が通る良訳だと思う。
でも、日本語では曖昧にできた主語、反対に数文字で書けていた深遠なことばが歯抜けて気が抜けたようになっている。読者のこころをつかむ一文として、断然原著のほうが優れているように思える。
もちろん翻訳輸出するものばかりではない、翻って輸入されてくる文章たちは、海外の詩や戯曲は、きっとたくさん韻を踏んで、技巧を凝らして、内容のすばらしさだけでなく文としての見栄えも素晴らしいと評価されたはずだ。それが崩れちゃうんだろうなあという気がしている。
そういうわけで、構文の壁に阻まれて、原著ならではの味わいを、翻訳本は伝えられない。
ひいては、原著よりすばらしい翻訳本はない、と思っていました。
この考えは今も変わらない。
でも、冒頭の『翻訳本の楽しみは原著に劣る』という考えについては、最近改心したんです。
きっかけは、シェイクスピアの『ハムレット』。
シェイクスピアの四大悲劇のひとつとして知られ、なかでも「To be, or not to be: that is the question.」という台詞が有名です。生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。
ぶっちゃけ、現代文だろうが古典だろうが、著作権切れ以前の作品って苦手だったんですよ。
中高の授業のせいにするんじゃ逃げだ!といわれても仕方ないけれど、
古典ってなんだか、今の文体と違って読みにくいし、授業でやった作品のなかで大して心を揺さぶられた経験もなく、味気ないものだと思っていました。
きっと、今の人とむかしの人とじゃ感性が違っているのだ、私はそういうのよくわからん、と思って逃げていました。
唯一著作権切れで好きな作品といったら『走れメロス』くらいかも。我が輩は猫である、も、長ったらしいばかりで何が楽しいのか、と学生の私にはなじまなかった。羅生門は怖さでおもしろさなんか吹っ飛ぶし、むかしの人のホラーはガチすぎる。
というわけで、海外作品の古典なんかさらに縁遠いってものです。小学生の頃からさんざん本を読んでいても、古典という星の周りばかりをつかんでいたように思います。古典てのは怖い、つまらん、授業の教材だと。
んで、シェイクスピアに初めて触れたのがなんとこの年ですよ。1985年生まれなので気になる人は計算してください。
きっかけは、これまた先日の図書館と同じようにたわいのないもので、漫画本を読んでいてですね。
絶園のテンペストという作品が、やたらとシェイクスピアをひいてくるものだから、ちょうど図書館も使えるし読んでみるかと。
絶園のテンペスト 1 (ガンガンコミックス)

※大本の流れ:
絶園のテンペストのOPかっけーっす(※今期アニメ版放映中)
> あれ、アニメ版見てみたら結構おもしろい
> 一日で原作漫画版全巻読破
> ハムレットとテンペスト読むか←イマココ!
どうだ!実に安易だろう!
しかし、世の中安易に行動してみるもんである。図書館で借りたハムレットを、帰りの山手線で読み出して、余計に一周してしまった。
※もちろんルール違反だから、JRさんには平謝りするしかない。ごめんなさい、許して。
もーやばい。止まらない。
あらすじをうーーーっすら知ってはいたが、ほとんど前知識なしで読み始めたのが奏功した。
読み始めたら、本が手にくっついて離れない。手が次のページを繰ろうとうずうずして、目はレーザービームを当てるみたいに集中して、文字の意味をさらっていく。
読み終わったあとにも、もうなんだか感動してしまって。
もちろん、本が面白かったことが何よりの幸せ。けれど、それとはまた別に、学生の頃みたいにのめり込むような読書が、まだ私にもできるんだと。
こんな読書は何年ぶりだろう。
覚えているのは、ハリーポッターシリーズが、確か3巻くらいまでハードカバーで出ていた頃だとおもうが、2巻までを買ってもらい、読み始めたところ一晩で1巻2巻を平らげた。本当におもしろい本に出会うと、眠たくなんかならない、逆に目がスパッっと冴えて大変なことになる。2巻を読み終えて、あまりのおもしろさにじたばたし、早く3巻を買いに行きたい!と心底願ったものだった。
そういう幸せな読書に、そういえばここ数年出会っていなかったなあと思い出す。
理由は明快なのだけれど。
なにせ、小説を読まなかった。
自己啓発とか、ビジネスとか、社会問題とか差別のはなしとか
一見賢くなれそうな本ばかりを飲み食いして、ついには通風を起こしかけていたのだ。
最近、本がつまらないなあと思い、それはもちろん偏食の限りを尽くしたからだった。
自己啓発とか、ビジネスとか、社会問題とか差別のはなしとか
そういうものばかり腹に詰め込めば、そりゃあ似たような味に飽きがきて、栄養バランスだってよろしくない。
賢くなろうとせず、単純に楽しむという読書が長いことできていなかった。
そんな読書が、まさか敬遠していた古典の中でできるなんて、どうして想像できるだろう?
期待なんてゼロだった。絶園のテンペストの裏読みができればもっとおもしろくなるだろうという、別の本の味付け程度にしか考えていなかったのに。
でもそうなった。本との出会いも、人との出会いくらい唐突で、奥ゆかしいものだと、こんなに幸福になる時間って、人生の中でもそう何回もない。
ベストではない代わりに、沢山のハムレットがある
初めて読んだハムレットは、松岡和子訳版でした。これは、絶園のテンペストが採用している野島秀勝訳版とは違う。でも、最初にこちらを読んでよかったと思いました。野島訳は、ちょっと言い回しが古めかしい。もちろん、とても面白く読める。読めるけれど・・・もしこちらを先に読んでいたら、わずかな読みづらさが、きっと私の頭に冷や水をかけたろうと思う。おもしろいけれど、ここまで深い没頭はきっとできなかった。そういう意味で、河合祥一郎の『新訳 ハムレット』もいい。訳はだいぶ松岡和子訳に近い。
そう、これが、翻訳版の楽しみだ。
松岡和子訳を読み終わった後で、私はいくつかの表現が気になった。
たとえば、『俺はオフィーリアを愛していた』のくだりだ。
松岡訳の『実の兄が四万人束になっても』というのは、想像するとちょっと笑えてしまう。河合訳でも『四万人の兄貴の』となっているので、たぶん原文がそのようになっているのだろうけれど、だったら少し曲げてでも、野島訳のように『たとえ幾千幾万の兄があり』というほうが、こう、なんというかシリアスを壊さないと思う。四万人、と数字を言われると、四万人分の兄がそぞろ歩く図を脳裏に描いてしまうが、幾千幾万ならミクロよりマクロへ視点が動いて、実際にお兄さんたちを想像をせずに済む。
この訳は、松岡版より野島版の方が好きだ、とか。
若い王子ハムレットの狂気、あのシーンはどの訳が一番雰囲気が出ていて好きだ、とか。
比べて読むのがとても楽しいと気づいた。
この楽しみは、きっと原著のある国では味わえないだろう。
原著には原著ならではの、すばらしい表現、韻の踏み方、その国の文化を背景とする共通認識が潜んでいる。それは原著でなければ、あるいはその原著を生み出した土地でなければ味わえない唯一無二のものだ、きっと。
だから、原著がナンバーワンのオンリーワンだとおもっていたのだ。それは今も変わらない。
でも、翻訳された古典には、ナンバーワンでもオンリーワンでもない代わりにそれらを比較して楽しむという、読み方の豊かさがあることに気づいた。
古典から逃げていたツケでこんな幸福を見逃していたけれど、今日知れたのは幸福だ。
翻って、20代のうちに知れたのはとても幸福だったと、最後には思えるのかもしれない。
 |
ハムレット (岩波文庫) シェイクスピア SHAKESPEARE 岩波書店 2002-01-16 |
 |
シェイクスピア全集 (1) ハムレット (ちくま文庫) W. シェイクスピア William Shakespeare 筑摩書房 1996-01 |
 |
新訳 ハムレット (角川文庫) シェイクスピア 河合 祥一郎 角川書店 2003-05-25 |